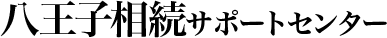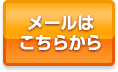こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
人生の中で、親からの贈与を受ける機会は数回あるかもしれませんが、住宅をもらうのはそう多くはありません。
しかし、相続よりも早いタイミングで自宅を譲りたいという親の意向や、子の住宅取得をサポートしたいという考えから、「住宅の贈与」という選択がされることがあります。
ここで注意しておきたいのが「贈与税」です。住宅は高価なものですから、多くの場合、贈与の基礎控除内に納まらず、贈与税が生じます。
目次
【生前贈与における贈与税とは?】
贈与税とは、個人から財産をもらった場合にかかる税金で、年間110万円の基礎控除を超える部分に対して課税されます。たとえば、親から2,000万円相当の住宅を贈与された場合、110万円を引いた1,890万円が課税対象となります。
贈与税の税率は累進課税となっており、もらった財産の金額が大きくなるほど税率も高くなります。そのため、何の対策もせずに住宅を贈与されると、多額の税金が発生してしまう可能性があるのです。
なお、住宅の評価額の方法は以下のとおりです。
- ・建物の評価額=固定資産税評価額
- ・土地の評価額=路線価方式or倍率方式
路線価方式と倍率方式のどちらの適用になるかはエリアごとに分かれるので、国税庁のホームページで確認します。
【贈与税の他にも注意が必要】
不動産を贈与された場合は、贈与税のほかに「不動産取得税」や「登録免許税」もかかります。
また、名義変更の登記費用も必要になります。これらのコストも含めて、総額でどのくらいの負担が生じるのかを事前に確認しておくことが重要です。
【住宅の贈与には特例がある】
住宅の贈与にはいくつかの方法があります。一つは「不動産そのもの」を贈与する方法。もう一つは「住宅購入資金」として現金を贈与する方法です。
購入資金の贈与に関しては、国としても支援制度を設けています。その制度とは、「住宅取得等資金の贈与の特例」であり、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となります。
2025年4月時点では、省エネ基準を満たす住宅を取得する場合、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。これは親や祖父母からの贈与に限られますが、非常に大きな節税効果が期待できます。
※非課税限度額は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外だと500万円です。
なお、この特例は受贈者が新たに住宅を取得・新築・増改築し、一定の期限内に居住することを条件としています。すでに存在する住宅をそのまま贈与する場合、これらの要件を満たさないため、特例の適用対象外となります。
【相続で引き継ぐ場合の違い】
(1)控除枠や税金面で見る違い
●贈与の場合のポイント
単純な税率だけ見れば、贈与税は相続税に比べて税率が高いと言えます。また基礎控除も年間で110万円なので、相続の基礎控除と比較すると少額です。
ただし、住宅取得等資金の贈与に使える非課税特例を使えば、一定額まで税金を抑えられます。
住宅取得等資金の非課税:最大1,000万円(省エネ住宅など)
●相続の場合のポイント
相続税の方が単純比較すると贈与税よりも税率は低めで、基礎控除も大きい(3,000万円+600万円×相続人の数)と言えます。
さらに、相続では「小規模宅地等の特例」があります。これは、被相続人の自宅を相続する際に、土地の評価額を最大80%減額できるものです。これも非常に大きな節税ポイントです。
なお、建物や土地の評価は贈与でも相続でも同じです。
(2)名義変更や登記・取得税の違い
贈与では不動産取得税や登録免許税がかかります。贈与の場合は、登録免許税が2%で、不動産取得税は3%です。
しかしながら、相続では軽減措置があります。登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」に軽減します。不動産取得税は非課税です。
この点でも相続の方が、コストが少ないです。
(3)トラブル回避や生前対策としての贈与
税金面では相続の方が有利と言えます。ですが、「生前に確実に財産を渡したい」「遺産分割でもめたくない」といった理由から、あえて生前贈与を選ぶ人も多いです。
たとえば、長男に住宅を確実に渡したい場合、配偶者の生活基盤を整えておきたい場合、などの理由です。
生前贈与には早くから財産を移転できるというメリットが大きいのです。
【専門家への相談は必須】
住宅贈与は金額が大きく、税務上の手続きも煩雑になりがちです。税務署への申告だけでなく、法務局での登記、自治体での不動産取得税の申告など、複数の機関とのやり取りが必要です。
また、特例利用の際には要件を満たす必要もあるため、できる限り専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
【生前贈与の相談は八王子相続サポートセンターへ】
住宅の贈与は、親から子への大きなサポートであると同時に、税務上の大きなイベントでもあります。贈与税の負担を軽減するための特例制度もある一方で、その適用には多くの条件があるため、事前の準備と情報収集が不可欠です。
「贈与すれば安心」ではなく、「どう贈与すれば負担を少なく、安全に贈与できるか」が重要です。節税を図りながら、家族の将来を見据えた贈与計画を立てましょう。
生前贈与や相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。