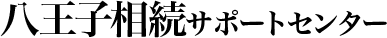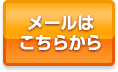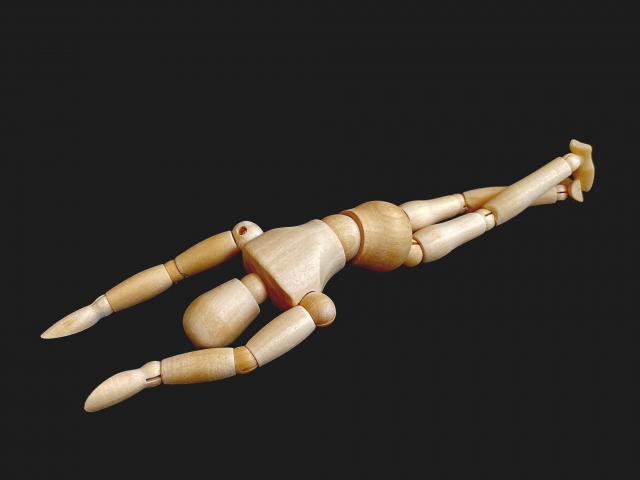
こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている 税理士 の古川顕史です。
相続において、遺産は基本的に故人の配偶者や子供に引き継がれます。これは、配偶者や子供が民法で定める法定相続人だからです。(子供がいない場合は配偶者と両親になります。)
しかし、遺言を活用すれば、法定相続人以外の人にも財産を譲ることが可能です。このように遺言によって特定の個人や団体に財産を譲る行為を「遺贈」と言います。
遺贈では、誰に財産を渡すかは遺言者の自由です。孫、友人、会社の同僚、さらには慈善団体や法人に対しても遺贈することができます。
しかし、せっかく遺言書で受取人を指定しても、相続の時点でその受遺者がすでに亡くなっていた場合、その遺産はどうなるのでしょうか。
目次
【遺贈と受遺者について】
遺贈とは、遺言によって被相続人(故人)が自身の財産(全部または一部)を、特定の人物や団体に無償で譲ることを指します。遺贈を受ける人のことを「受遺者」と言います。
受遺者は、法定相続人に限定されません。たとえば、知人、恩師、企業、さらには慈善団体など、遺言者が希望する相手に財産を渡すことができます。
遺贈と相続は似ていますが、異なる点もあります。相続は、民法によって定められた法定相続人に自動的に発生するものです。
つまり、被相続人の配偶者や子供など、法律で定められた親族が相続する権利を持ちます。一方、遺贈は遺言者の意思によって財産を譲るものであり、法定相続人でない人物にも財産を受け取る権利を与えることができます。
【受遺者が死亡している場合】
遺言書で指定された受遺者が亡くなっていた場合、遺産はどうなるのでしょうか。
民法によれば、遺言書で指定された受遺者が、遺言者よりも先に死亡している場合、その遺贈は「無効」となります。これは、民法第994条に記載されており、受遺者が遺言者より前に死亡していた場合、その受遺者が受け取るべき財産は無効となることが定められています。
遺言書が効力を持つのは遺言者が亡くなった時点です。つまり、遺言書の内容に従って財産を受け取るべき人が存在していない場合、その部分は遺言書の効力を持ちません。
このため、遺言書の作成時に受遺者が健在であったとしても、相続時に亡くなっていた場合、その指定された財産を受け取ることができなくなります。
【受遺者は代襲相続が起こらない】
相続の場合、法定相続人が亡くなっていると、その子供(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。しかし、遺贈においてはこの制度は適用されません。
つまり、遺言によって指定された受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合、その受遺者の子供が代わりに遺産を受け取ることはできません。そのため、受遺者がすでに死亡している場合、その部分の遺贈は無効となり、遺言書に記載されていない財産として扱われることになります。
この場合、遺産の分割は法定相続人全員での話し合いによって決定されます。遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して財産の配分を決めることになります。
【予備的遺言の活用】
このような問題を避けるためには、「予備的遺言」を活用することが有効です。
予備的遺言とは、遺言書において、指定した受遺者が死亡した場合に備えて、別の受遺者を指定しておくことです。
- 例文:
- 第〇条 遺言者は、下記の財産を、遺言者の友人Aに相続させる。(財産の詳細を記載)
- 第△条 遺言者は、Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、上記の財産をその息子のBに相続させる。
このように、遺言書の中に予備的遺言を加えておくことで、受遺者が亡くなった場合でも、スムーズに遺産を引き渡すことが可能になります。
【遺言書がない場合のリスク】
遺言書がない場合、遺産は法定相続人間で分割されることになりますが、この際には思わぬトラブルが発生することもあります。
例えば、実際には関係が薄いと感じていた親族が突然相続人として現れることもあり得ます。これは、法定相続人の範囲が予想以上に広いためです。例えば、片親が異なる兄弟姉妹が相続人として現れるケースもあります。そのため、遺言書を作成していない場合、思いもよらない相続人が現れて、遺産分割の際に争いが起きる可能性があります。
【トラブルを避けるために遺言書の作成を】
相続に関するトラブルは、どの家庭でも起こりうる問題です。「自分の家族には関係ない」と考えていても、遺産分割を巡る争いは予期せぬ形で発生することがあります。
特に、子供がいない夫婦の場合、先に挙げたように予期せぬ相続人の出現により、配偶者だけで遺産を分けることが難しくなることがあります。そのため、遺言書を作成して、自分の意志を明確に示すことは非常に重要です。
遺言書を作成する際は、公正証書遺言を利用する方が望ましいです。公証役場で作成される公正証書遺言は、原本が役場に保存されるので紛失や改ざんのリスクも少なく、安心して利用できます。
なお、自筆証書遺言を選ぶ場合でも、法務局が原本を管理してくれる「自筆証書遺言保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
トラブル回避のために遺言書を作成することは大切であり、相続で確実に遺族に渡るように最適な形式を選択することも重要です。
【相続についての相談は古川会計事務所まで】
遺言書で指定した受遺者が亡くなっている場合、その部分の遺贈は無効となります。代襲相続も適用されず、受遺者が死亡した後の遺産分割は相続人全員で協議して決定することになります。
遺言書を作成する際には、予備的遺言を盛り込んでおくことで、受遺者が死亡した場合に備えることができます。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。